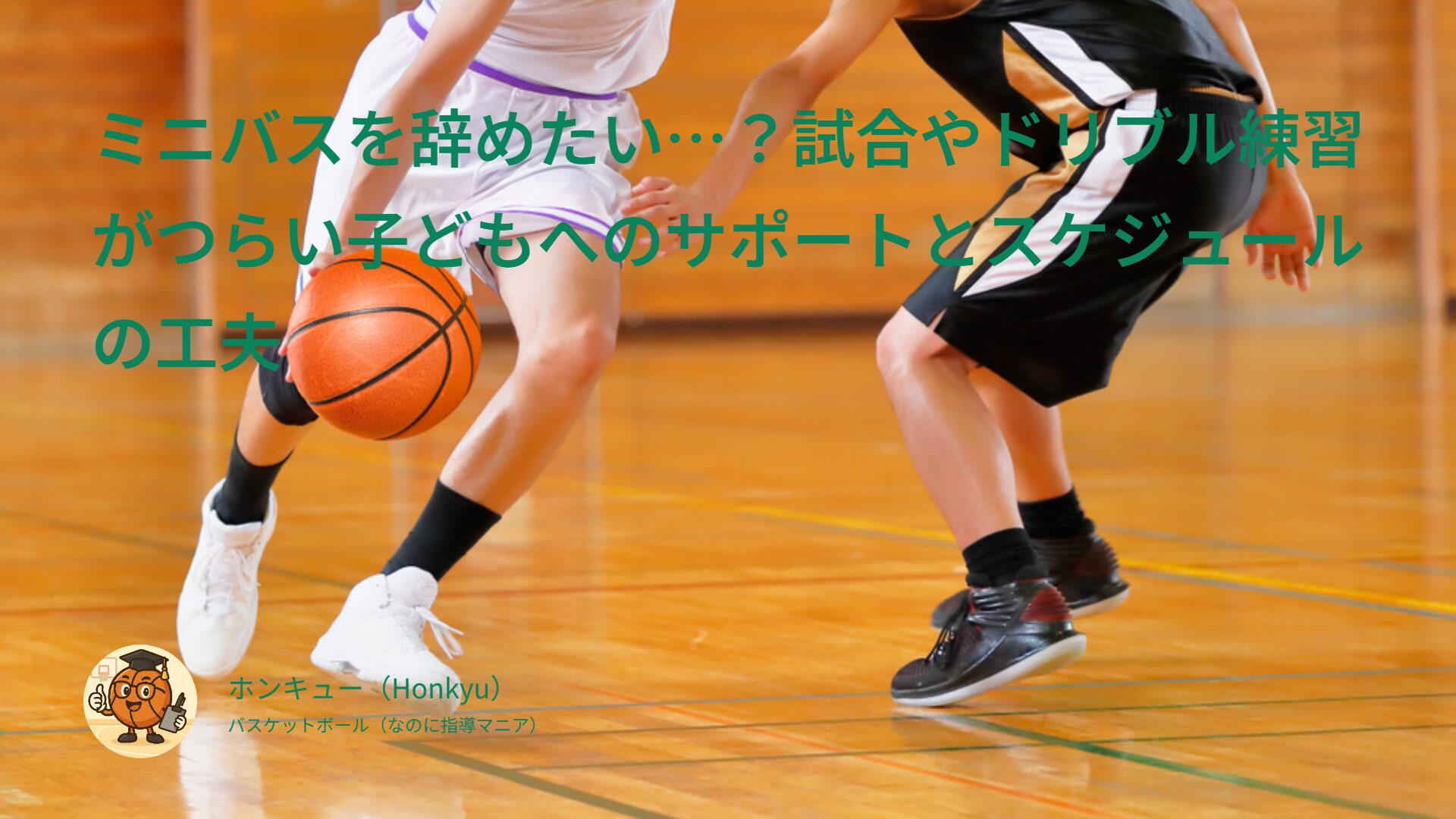ミニバスで伸びる子の特徴11選!親ができる才能の育て方

「うちの子はミニバスで伸びるだろうか?」多くの方がそんな期待と少しの不安を抱えているのではないでしょうか。ミニバスで伸びる子の才能を見抜く特徴には、実は共通点があります。バスケに向いている子はどんな子ですか?という問いの答えは、単に足が速い、背が高いといった身体能力だけではありません。
この記事では、そもそもスポーツで伸びる子の特徴から、上手い子の特徴に見るバスケIQと身体能力、そしてセンスのある子に共通する動きの質まで、多角的に解説していきます。選抜に選われる子の思考と行動パターンや、チームを勝利に導くエースになる子の条件を知ることで、お子さんの持つ可能性に気づくことができるでしょう。
また、親子で実践!ミニバスで伸びる子の育成法として、成長の鍵を握るバスケのゴールデンエイジはいつですか?という疑問や、急に上手くなる子の成長スパートの秘密にも迫ります。下手な子の親ができるサポートと心構えから、時には避けて通れないチーム内の意地悪な子への対処法とはまで、具体的な悩みにも寄り添います。この記事を最後まで読めば、まとめ:ミニバスで伸びる子はいつからうまくなる?という最終的な疑問へのヒントが見つかるはずです。
- ミニバスで伸びる子の具体的な身体的・精神的特徴がわかる
- 子どもの才能を最大限に引き出すための親の関わり方を学べる
- 成長が著しい「ゴールデンエイジ」の効果的な活かし方がわかる
- 練習やチーム内の課題に対する具体的な解決策が見つかる
ミニバスで伸びる子の才能を見抜く特徴

- バスкеに向いている子はどんな子ですか?
- そもそもスポーツで伸びる子の特徴は?
- 上手い子の特徴に見るバスケIQと身体能力
- センスのある子に共通する動きの質
- 選抜に選ばれる子の思考と行動パターン
- チームを勝利に導くエースになる子の条件
バスケに向いている子はどんな子ですか?
バスケットボールに向いている子というと、天性の運動神経があり、他の子よりも背が高いといった身体的なアドバンテージを持つ子をイメージするかもしれません。もちろん、それらの要素は有利に働くことがありますが、何よりも大切なのは「バスケットボールが好き」「楽しい」という純粋な気持ちです。この気持ちこそが、困難な練習を乗り越え、成長し続けるための最大のエネルギー源となります。
具体的には、身体的な特徴だけでなく、精神的な側面も含めて以下のような特徴を持つ子がバスケに向いていると言えるでしょう。
体を動かすことや走ることが好き
バスケットボールは、オフェンスとディフェンスが目まぐるしく入れ替わり、試合中は常にコートを走り回ることが求められるスポーツです。そのため、じっとしているよりも体を動かすことが好きで、走ることに喜びを感じられる子は、バスケの持つダイナミックな魅力を存分に楽しむことができます。練習の厳しいランメニューなども、前向きな気持ちで取り組めるでしょう。
チームプレイを好む
バスケットボールは5人の選手が連携してプレーする、まさにチームスポーツの代表格です。自分一人の力で勝利することはできません。だからこそ、仲間と協力して一つの目標に向かうことに喜びを感じられる協調性は、非常に重要な資質となります。仲間を尊重し、良いプレーを称え、ミスをカバーし合う。そうした円滑なコミュニケーションを取ろうとする姿勢が、個人だけでなくチーム全体の成長につながるのです。
向上心があり負けず嫌い
「もっと上手くなりたい」「昨日の自分を超えたい」「試合に勝ちたい」という強い向上心は、地道で反復的な基礎練習を続けるための大きな原動力です。ミスをしても落ち込むだけでなく、「次はどうすれば成功するか」を考えられる前向きな姿勢が大切です。また、ライバルの存在が良い刺激となり、自分の成長を加速させる負けず嫌いな一面も、トップレベルを目指す上では欠かせない要素になります。
小柄な子や運動が苦手な子でも大丈夫!
ミニバスでは、身長の高さだけが全てではありません。スピードを活かして相手ディフェンスをかき乱すポイントガードや、コート全体を見渡して正確なパスを供給する司令塔など、様々な役割があります。身長や運動神経に自信がなくても、自分の持つユニークな強みを見つけ、それを磨くことでチームに不可欠な選手として活躍できるのが、バスケットボールの奥深い魅力なのです。
そもそもスポーツで伸びる子の特徴は?

バスケットボールという競技の枠を超えて、あらゆるスポーツで大きく成長していく子どもたちには、技術的な才能以前の「人間性」や「思考の習慣」に共通する特徴が見られます。これらは、スポーツの技術という家を建てるための、頑丈な土台となる非常に重要な要素です。
ここでは、その中でも特に重要な3つの力について掘り下げてみましょう。
1. 素直さと傾聴力
コーチや経験豊富な先輩からのアドバイスを、「なるほど、まずはやってみよう」と素直な心で聞き入れ、すぐに実践できる子は飛躍的に成長します。自分のやり方や考えに固執せず、人の話を真剣に聞き、良いと思ったことを貪欲に吸収しようとする姿勢が大切です。伸びる子は、まるで乾いたスポンジが水を吸い込むように、様々な知識や技術を吸収していきます。
2. 自分で考えて行動する自主性
指導者から言われた練習メニューをただこなすだけでなく、「なぜ今、この練習が必要なのか」「試合で活躍するために、自分に足りないものは何か」を常に自分で考え、主体的に行動できる子は大きく伸びます。チームの練習時間外に自主的にシューティングをしたり、自分の課題を克服するためのトレーニング方法を調べたりする姿勢が、周りの選手との間に確かな差を生み出します。
3. 粘り強さとやり抜く力(GRIT)
練習の成果がすぐに現れなくても、簡単に諦めずにコツコツと努力を継続できる力は、長期的な成長を遂げるための最も重要な鍵と言えるでしょう。試合での敗北や自身のミスといった失敗を経験しても、それを糧にして「次こそは絶対に勝つ」と前向きに取り組める粘り強さが求められます。一度決めた目標に向かって、最後までやり遂げようとする意志の強さ、すなわち「GRIT(やり抜く力)」が、大きな成長の原動力となるのです。
これらの「素直さ」「自主性」「やり抜く力」は、スポーツの分野で成功するためだけでなく、将来社会に出て様々な困難に立ち向かう際にも必ず役立つ、「生きる力」そのものですね。
上手い子の特徴に見るバスケIQと身体能力

ミニバスの試合で「あの子は上手いな」と周囲を唸らせる子は、単に身体能力が高いだけではありません。その質の高いプレーを支えているのは、「バスケIQ」と呼ばれるバスケットボール特有の状況判断能力と、その判断をコート上で瞬時に表現するための優れた身体能力、この二つの要素が高いレベルで融合している点にあります。
バスケIQ:コート全体を把握し、未来を予測する力
バスケIQが高い子は、ボールを持っているかどうかにかかわらず、常に首を振り、コート全体の状況を立体的に把握しようとします。ボールだけを一点集中で見るのではなく、味方や相手の位置、どこにスペースが生まれているかを常に「キョロキョロ」と観察し、コンマ数秒後の未来を予測しています。これにより、相手の意表を突くプレーや、チームを有利にする最適な選択が可能になるのです。
このバスケIQの高さは、具体的に以下のようなプレーに現れます。
- ディフェンスを引きつけておいて、ノーマークの味方に絶妙なタイミングでパスを出す
- 相手のパスコースを予測してカットを狙うインターセプト
- パスをもらう前から次の展開を読んでおり、ボールを受けたらすぐに次のプレーに移れる(キャッチ&シュート、キャッチ&ドライブなど)
- 相手ディフェンスが最も嫌がる位置やスペースに動くオフボールの動き
身体能力:イメージを正確に体現する力
どれだけ高いバスケIQによって最善のプレーをイメージできたとしても、それを実行するための身体能力が伴わなければ意味がありません。上手いと評される子は、特に以下の能力に優れており、頭の中のイメージを正確にコート上で体現できます。
- 走力:速攻やリターンなど、攻守の素早い切り替えに対応するスピードとスタミナ
- アジリティ(敏捷性):ディフェンスをかわす急な方向転換やストップ&ゴーを可能にする能力
- ボディバランス:相手との接触プレーにも体勢を崩さず、シュートやパスの精度を維持できる体幹の強さ
- コーディネーション能力:ドリブルをしながら周りを見る、走りながらパスを受けるなど、二つ以上の動作を同時にスムーズに行う能力
バスケIQを高めるには?
バスケIQは、日々の練習や試合の経験を通じて磨かれるのはもちろんですが、質の高いインプットによっても養われます。例えば、NBAやBリーグなどプロの試合をたくさん観ることは非常に効果的です。「なぜ今このプレーを選択したのか?」「自分だったらどうするか?」と考えながら観戦することで、プレーの意図を読み解く力がつき、自分のプレーの引き出しを増やすことにつながります。
センスのある子に共通する動きの質

指導者や保護者が「あの子はバスケのセンスがある」と感じる時、その選手の動きには、どこか無駄がなく、流れるようにしなやかな印象を受けるものです。この抽象的な「センス」の正体の一つが、「ボディハンドリング」能力の高さ、つまり自分の体を空間内で思い通りに、そして効率的に操る能力です。
ボディハンドリング能力が高いと、頭の中で描いた理想の動きと、実際の体の動きとの間に生じるズレが極めて少なくなります。これにより、ボールを巧みに扱う技術(ボールハンドリング)はもちろん、ディフェンスをかわすための複雑なステップワーク、安定したシュートフォームの習得などが非常にスムーズに進むのです。いわば、高性能なOSが搭載されたコンピューターのように、様々なスキルを効率よくインストールできる状態と言えるでしょう。
ボディハンドリングは後からでも飛躍的に伸ばせる!
ボディハンドリングや運動神経は、生まれ持った天性の才能だと思われがちですが、近年のスポーツ科学では、適切なトレーニングによって後からでも十分に向上させることが可能だと考えられています。重要なのは、自分の体の各パーツが今どこにあって、どのように動いているかを脳に正しく認識させる「ボディマップ」を精密に整えていくことです。
例えば、目をつぶって自分の鼻を正確に触ったり、指定された位置に関節を動かしたりするような簡単なトレーニングでも、ボディマップのズレを修正する効果があります。この「脳と身体の連携」を強化するトレーニングを地道に続けることで、プレーの質は劇的に変わる可能性を秘めているのです。
選抜に選ばれる子の思考と行動パターン
市や地区の選抜チームなどに選出される子は、高いレベルの技術力を有していることはもちろんですが、その根底にあるバスケットボールに対する意識の高さや、日々の行動習慣においても、他の選手とは一線を画す明確な特徴を持っています。
常に上を目指す思考と高いレベルでの自己評価
選抜されるレベルの子は、現状に満足することがありません。自分のプレーに対して常に客観的で、かつ批判的な視点を持ち合わせています。試合や練習の後には、「何ができて、何ができなかったか」「どうすればもっと良くなるか」を自分で言語化して振り返る習慣が自然と身についています。コーチからのフィードバックを素直に受け入れ、それを次の練習の具体的な課題として設定する、高いレベルでの自己分析能力に長けているのです。
バスケットボールを最優先する生活習慣と自己管理能力
高い目標を掲げる子は、バスケットボールが生活の中心にあります。それは単に練習時間が長いということだけではありません。自分のパフォーマンスを最大化するために、食事の内容や栄養バランスに気を配ったり、十分な睡眠時間を確保して体の回復を促したりと、アスリートとしての自己管理能力が非常に高いレベルにあります。自分の目標達成のために、何をすべきで、何をすべきでないかを理解し、それを実行できる強い意志を持っているのです。
チームへの強い貢献意識とリーダーシップ
個人として技術的に優れているだけでなく、「このチームを勝たせるために、自分に何ができるか」を常に考えて行動しています。自分が得点することだけでなく、厳しいディフェンスで相手のエースを抑えたり、大きな声を出してチームメイトを鼓舞したりと、数字には表れない部分でチームに貢献することの重要性を理解しています。チーム全体のパフォーマンスを高めるための行動を、誰に言われるでもなく自然に取ることができるのです。
選抜チームに選ばれることは、子どもにとって大きな自信となり、素晴らしい目標です。しかし、それがバスケットボール人生のゴールではありません。さらに高いレベルの仲間や指導者と出会い、バスケの新たな面白さや厳しさを学ぶための、貴重なスタート地点と捉えることが大切ですね。
チームを勝利に導くエースになる子の条件

チームのエースとは、単に試合で最も多く得点を取る選手のことではありません。チームが苦しい逆境にある時、「あいつにボールを託せば、きっと何とかしてくれる」と仲間やコーチから絶大な信頼を寄せられる、精神的な支柱となる存在です。真のエースと呼ばれる子には、卓越した技術、強靭な精神、そして模範となる行動の3つの面で、共通する条件が見られます。
| 要素 | 具体的な条件 |
|---|---|
| 技術(Skill) | 厳しいマークの中でも得点できるシュート力、勝負どころで確実にシュートを決めきる決定力。プレッシャーのかかるフリースローなどでも、普段通りのプレーができる技術的な精度と安定感。 |
| 精神(Mental) | 自身のミスを引きずらず、すぐに次のプレーに切り替えられるポジティブなメンタリティ。試合の勝敗を左右するクラッチタイムでも物怖じしない強い心臓。「自分がチームを勝たせる」という強い責任感と健全な負けず嫌い。 |
| 行動(Attitude) | 苦しい時こそ声を出してチームを鼓舞し、プレーで仲間を引っ張るリーダーシップ。誰よりも練習に真摯に取り組み、その背中でチームの模範となる姿勢。仲間からの信頼を勝ち得るための日々の努力。 |
エースの「わがまま」と「責任感」は紙一重
エースとしての「自分が決める」という強い責任感は非常に重要ですが、それが「自分さえ良ければいい」という独りよがりなプレー、いわゆる「わがまま」につながってはいけません。真のエースは、自分へのマークが厳しければ、仲間のチャンスを最大限に活かすパスを選択できる視野の広さを持っています。常にチームの勝利を最優先に考え、そのための最善の選択ができる選手こそが、真のエースと呼ばれるにふさわしいのです。
親子で実践!ミニバスで伸びる子の育成法

- バスケのゴールデンエイジはいつですか?
- 急に上手くなる子の成長スパートの秘密
- 下手な子の親ができるサポートと心構え
- チーム内の意地悪な子への対処法とは
バスケのゴールデンエイジはいつですか?
子どもの運動能力の発達過程には、特定の能力が飛躍的に伸びる「ゴールデンエイジ」と呼ばれる特別な期間が存在します。この貴重な時期の特性を保護者や指導者が正しく理解し、適切に活用することが、子どもの隠れた才能を最大限に引き出すための重要な鍵となります。
一般的に、バスケットボールにおけるゴールデンエイジは9歳〜12歳頃(小学校中学年〜高学年)を指します。文部科学省の資料でも示されているように、この時期は神経系の発達がほぼ100%に達し、大人のレベルに近づきます。そのため、新しい動きや複雑な技術を、指導者が見せたお手本を見ただけですぐに真似できてしまう「即座の習得」が可能になる、一生に一度のボーナスタイムとも言えるのです。
このゴールデンエイジに身につけた自転車の乗り方や水泳の感覚を忘れないのと同様に、バスケットボールの正しいフォームやステップワークといった技術や感覚は、体に深く、そして永続的に刻み込まれ、一生の財産になると言われています。
ゴールデンエイジの最も効果的な過ごし方
この時期に最も重要なのは、特定の専門的な動きだけを過度に反復させるのではなく、できるだけ多様な種類の動きを経験させることです。バスケットボールの練習はもちろんですが、例えば公園で鬼ごっこをしたり、木に登ったり、他のスポーツに挑戦したりすることを通じて、体の使い方やバランスの取り方を多角的に学ぶことが推奨されます。これにより、脳から筋肉へとつながる神経回路が豊かになり、将来的に高度な専門技術を習得する際の強固な土台が築かれるのです。
ゴールデンエイジを過ぎても決して遅くはありません
ゴールデンエイジは確かに成長における絶好の機会ですが、この時期を過ぎたらもう伸びしろがない、ということでは決してありません。中学生以降は、身長や体重といった骨格や筋力が大きく発達する「セカンドゴールデンエイジ」に入り、パワーやスピード、スタミナといった身体能力が飛躍的に向上します。どの年代にもそれぞれの成長のタイミングがあるため、焦らず、その時期の発達段階に合った適切なトレーニングを行うことが何よりも大切です。
急に上手くなる子の成長スパートの秘密
ミニバスの現場で、「あの子、夏休み明けに急に上手くなったな」といった会話を耳にすることがあります。これは決して気のせいではなく、子どもの成長過程でしばしば見られる現象で、いくつかの要因がタイミングよく重なることで起こる「成長スパート」です。
その主な要因は、「身体的な成長」というハードウェアの進化と、「精神的な成長」というソフトウェアのアップデートが、同時に起こることにあります。
1. 身体的な成長(ハードウェアの進化)
特に小学校3〜4年生頃になると、多くの子どもが第二次性徴期前の成長期に入ります。身長がぐんと伸び、それに伴い手足が長くなることで、今までどうやっても届かなかった高い位置のリバウンドが取れるようになったり、ディフェンスで相手に与えるプレッシャーが格段に増したりします。また、筋力が発達することで、シュートが楽にゴールまで届くようになり、フォームの安定につながったり、より力強いドリブルで相手を突破できるようになったりと、プレーの幅が物理的に大きく広がります。
2. 精神的な成長(ソフトウェアのアップデート)
体の成長と歩調を合わせるように、バスケットボールというスポーツそのものへの理解度も飛躍的に深まります。複雑なルールや基本的なチーム戦術を理解し、「今、自分は何をすべきか」をコートの中で考えながらプレーできるようになります。これまで感覚的に捉えていたコーチの抽象的な指示(例:「もっとスペースを広く使え」)も、その意図を論理的に理解できるようになり、練習の質そのものが劇的に向上するのです。
この「急に上手くなる」という目に見える現象は、それまで水面下でコツコツと続けてきた基礎練習の成果が、心と体の成長というきっかけを得て、一気に花開く瞬間でもあります。伸び悩んでいるように見える時期でも、子どもの中では確実に力が蓄えられています。その見えない努力と可能性を信じて、継続的なサポートを続けることが重要です。
下手な子の親ができるサポートと心構え

「うちの子は周りの子に比べて、どうしても下手かもしれない…」と、我が子のプレーを見て心配になったり、焦りを感じてしまったりすることもあるかもしれません。しかし、親のその焦りや過度な期待が、子どもからバスケットボールを楽しむという最も大切な気持ちを奪ってしまう可能性があります。ここでは、子どもの成長を信じて温かく見守るための、具体的なサポート方法と心構えを紹介します。
最も大切なのは「他人と比較しない」という絶対的なルール
子どもの成長のスピードやタイミングには、驚くほど大きな個人差があります。チームのエースや兄弟と比べるのではなく、常に比較対象を「過去のお子さん自身」に設定しましょう。「半年前はできなかったドリブルができるようになったね」「前よりシュートが届くようになったじゃないか」と、具体的な成長を見つけて褒めてあげることが、子どもの自己肯定感を育む上で非常に重要なのです。
親ができる具体的なサポートと、良かれと思ってやってしまいがちなNGな関わり方を、以下の表にまとめました。
| 👍 OKなサポート(子どもの伴走者) | 👎 NGなサポート(子どもの評価者) | |
|---|---|---|
| 言葉かけ | 結果(シュートが入ったか)ではなく、努力した過程(良いフォームで打てたか)を褒める。「ナイスチャレンジ!」と失敗を恐れずに挑戦した勇気を称える。 | 「なんでできないの?」「もっと集中しなさい!」と結果や精神論で責める。他の子と比較して「〇〇ちゃんはできているのに」と評価する。 |
| 練習への関わり | 子どもが「練習したい」と言った時に一緒に楽しむ姿勢を見せる。自主練習しやすい環境(ボールやゴール、練習場所への送迎など)を整える。 | 親の熱意で無理やり練習させる。「お父さんがコーチになってやる」と家庭で過度な技術指導をしすぎる。 |
| 試合での態度 | 良いプレーもミスも全て含めて、ポジティブな声援を送る。試合後は結果にかかわらず、最後まで頑張ったことを労う。 | 観客席から大声で「走れ!」「シュートを打て!」などの指示やダメ出しをする。帰りの車の中で「今日の試合の反省会」を一方的に開く。 |
保護者の最も重要な役割は、技術を教えるコーチになることではなく、世界で一番の「ファン」であり「サポーター」であることです。技術的な指導はチームのコーチに信頼してお任せし、家庭では子どもが安心して挑戦でき、たとえ失敗しても大丈夫だと思えるような温かい安全基地を作ってあげましょう。
チーム内の意地悪な子への対処法とは

残念ながら、子どもたちが集うどのコミュニティにも、人間関係のトラブルは起こり得ます。もしお子さんがチームメイトからの心ない言葉や行動に傷ついていると感じたら、親として冷静かつ慎重に、そして毅然と対応することが求められます。感情的になったり、問題を放置したりすることは、状況をさらに悪化させる可能性があります。
大切なのは、親だけで抱え込まず、然るべき手順を踏んで対応することです。
ステップ1:子どもの話を否定せず、全て受け止める
まずは、お子さんの話を最後まで遮らず、否定せずに聞いてあげてください。「何があったのか」「その時どう感じたのか」を優しく受け止め、「話してくれてありがとう。お父さん(お母さん)は、あなたの絶対的な味方だよ」という姿勢を明確に示しましょう。これにより、子どもは一人ではないという安心感を得ることができ、心のケアの第一歩となります。
ステップ2:事実確認を冷静に、客観的に行う
子どもの話だけを鵜呑みにするのではなく、できる範囲で事実確認に努めましょう。他の保護者との会話の中で、それとなくチームの雰囲気について聞いてみるのも一つの方法です。ただし、この段階で感情的になって直接相手の子やその親に連絡を取ることは、トラブルを拡大させるリスクが高いため、絶対に避けるべきです。あくまで客観的な情報を集めることに徹します。
ステップ3:指導者(コーチ)に「相談」という形で伝える
チーム内で起きた問題は、チームの責任者である指導者に報告・相談するのが基本です。その際、「うちの子が〇〇くんにいじめられています!」と断定的に訴えるのではなく、「最近、〇〇(お子さんの名前)がチームに行くのを少し渋っていて、話を聞くとこういうことがあったようなのですが、チームでの様子はいかがでしょうか?」というように、あくまで「相談」という形で丁寧に伝えましょう。指導者にチーム全体の様子を注意深く見てもらうきっかけを作ることが目的です。
親が直接介入することの大きなリスク
保護者が当事者同士の問題に直接介入すると、感情的な対立に発展し、かえって問題を複雑化させてしまうケースが少なくありません。指導者という公平な第三者に入ってもらうことで、チーム全体の問題として冷静に対処してもらうのが最善策です。もし状況が改善しない場合は、日本スポーツ振興センターの相談窓口のような外部の専門機関に助言を求めることも検討しましょう。
まとめ:ミニバスで伸びる子はいつからうまくなる?

ミニバスケットボールで子どもが大きく成長するタイミングは、身体の成長やバスケ経験、そして本人の性格など、様々な要因が複雑に絡み合うため、一人ひとり全く異なります。「うちの子はいつになったら上手くなるのだろう?」と焦りを感じる前に、今回の記事で解説した様々な視点がお子さんの成長を温かく、そして長期的にサポートするためのヒントになれば幸いです。
最後に、この記事の重要なポイントを改めてまとめます。
- ミニバスで伸びる子の最大の共通点はバスケが好きという純粋な気持ち
- 走ることや仲間とのチームプレイを楽しめる子がバスケに向いている
- スポーツ全般で伸びる子は技術以前に素直さ・自主性・継続力を持つ
- 上手い子はコート全体を見るバスケIQとそれを実行する身体能力を兼ね備える
- センスの正体は自分の体を思い通りに操るボディハンドリング能力にある
- 選抜に選ばれる子は高い自己管理能力とチームへの強い貢献意識を持つ
- エースは技術力に加えプレッシャーを力に変える精神力と責任感が不可欠
- 9歳から12歳頃は新しい技術の習得に最適なゴールデンエイジ
- この貴重な時期に多様な運動を経験することが将来の大きな財産を作る
- 急に上手くなるのは心と体の成長タイミングが一致する成長スパート期
- 親の最も重要な役割は技術指導者ではなく世界で一番のサポーターであること
- 他人と比較せず過去の子ども自身と比べ「できたこと」を具体的に褒める
- 家庭では子どもが安心して挑戦し失敗できる温かい安全基地作りを心がける
- チーム内の人間関係トラブルは一人で抱えずまず指導者に相談するのが基本
- 子どもの成長スピードと可能性を信じ長い目で見守る姿勢が才能を開花させる
人気ブログランキング(クリック応援よろしくお願いいたします。)

ミニバスケットボールランキング