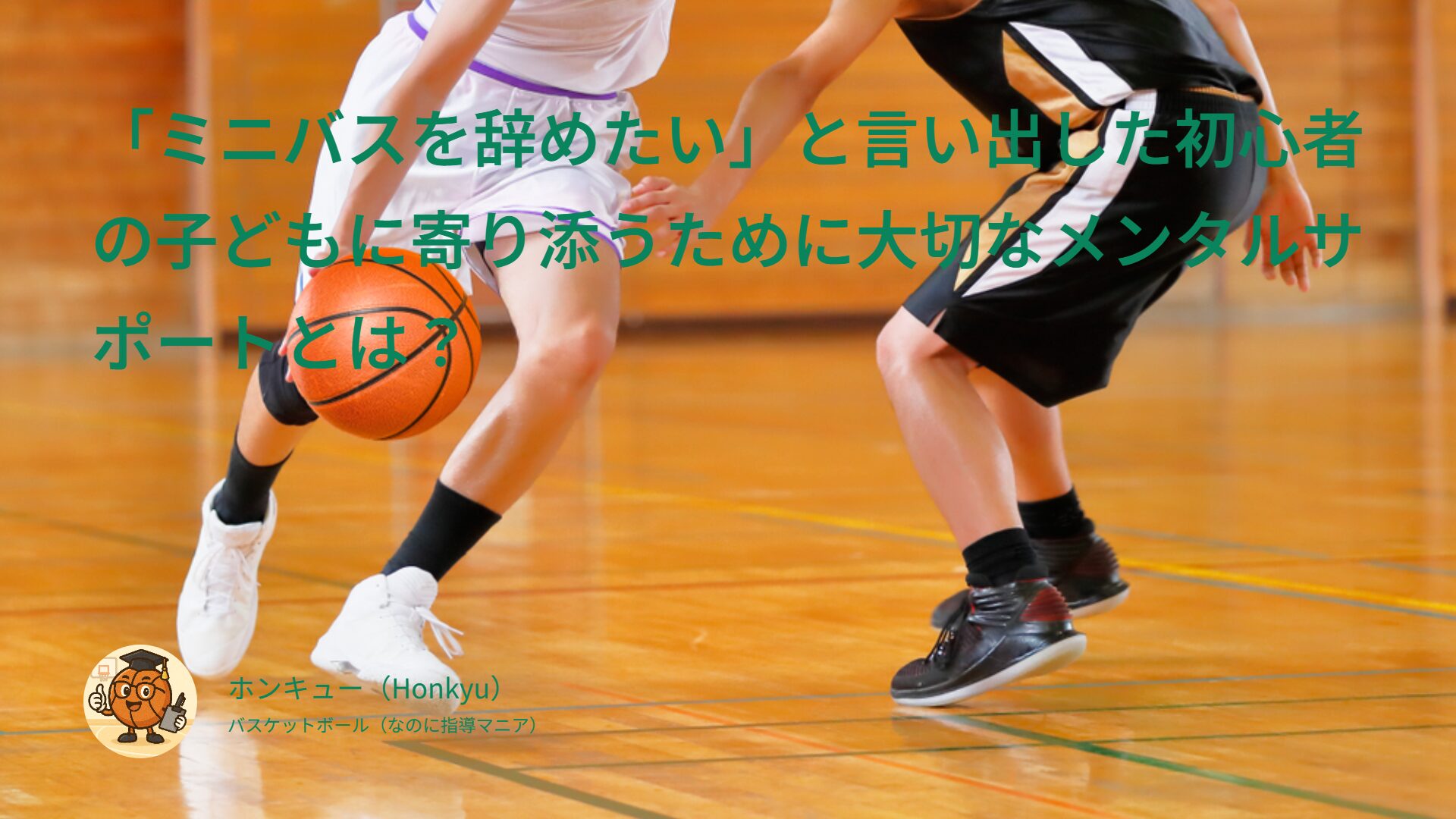ミニバスのボールサイズ変更はいつから?ルール改正を解説

ミニバスケットボールのルールが、未来の選手たちのために大きく変わろうとしています。特にミニバスのボールサイズ変更は、日々練習に励む選手や、それを支える保護者の皆さんにとって、非常に大きな関心事ではないでしょうか。現在、小学生が使うボールは現行の5号球ですが、ルール改正により6号球へ変更されることが正式に決定しました。
では、一体ミニバスはいつから6号サイズになった(なる)のでしょうか?この歴史的な変更は2025年から本格化し、ボールだけでなくゴールの高さも同時に変更される予定です。この記事では、ゴールの高さが変更されるのはなぜかという根本的な背景から、バスケットボールのサイズ6号は何歳から使うのが適切なのか、そして小学生から6号球で練習すべきかといった、現場での実践的な疑問まで、あらゆる角度から深く掘り下げて解説します。
さらに、バスケットボールの公式球は変更されるのか、コートサイズなど他のルール変更点はあるのか、そしてルールブックで最新情報を確認する方法まで、この総まとめ記事であなたの疑問をすべて解消します。
この記事でわかること
- ミニバスのボールサイズ変更の具体的なスケジュールと移行期間の詳細
- ボールサイズと同時に変更されるゴールの高さや3Pライン導入の背景
- ルール変更が選手のスキルやチーム戦術に与える具体的な影響
- 新しいルールに向けて選手やチームが今から準備すべきこと
ミニバスのボールサイズ変更!その概要とスケジュール

- ミニバスはいつから6号サイズになった?
- 小学生が使うボールは現行5号
- ルール改正で6号球へ変更
- ルール改正は2025年から本格化
- ゴールの高さも同時に変更される
- ゴールの高さが変更されるのはなぜ?
ミニバスはいつから6号サイズになる?
結論から言うと、ミニバスケットボールで6号球が正式に導入されるのは、2025年度に開催される全国大会から段階的に始まり、2027年度末までに全国で完全移行が完了する予定です。したがって、「なった」のではなく、現在まさに「なりつつある」過渡期と言えます。
つまり、2024年4月からすでに3年間の移行期間に入っており、準備が整った地域や一部の先進的な大会では、すでに新しいルールが試験的に適用され始めています。このルール改正は、日本バスケットボール協会(JBA)が、子どもたちの成長実態や技術レベルの向上といった現代的な変化に対応するため、長年にわたり検討を重ねてきたものです。3年間という移行期間は、各チームが新しいボールを準備したり、体育館などの施設がゴールの高さを調整したりするための、重要な準備期間として設けられています。
このように、全国一斉にルールが切り替わるわけではありません。地域ごとのバスケットボール協会や、各大会の主催者の判断によって導入ペースは異なります。そのため、所属するチームや地域の連盟から発信される情報をこまめに確認し、自身が参加する試合のレギュレーションを正確に把握しておくことが、これまで以上に大切になります。
移行期間とは?
2024年4月から2027年3月末までの3年間は、新しいルール(6号球、リングの高さ305cm、3ポイントライン)へ円滑に移行するための準備期間です。この期間中、大会主催者は、会場となる体育館のゴールが高さ調整に対応しているか、参加チームの選手たちが新ルールにどれだけ習熟しているかといった実情を総合的に考慮し、新ルールを適用するかどうかを柔軟に判断することが認められています。
小学生が使うボールは現行5号

現在のミニバスケットボールの公式ルールでは、小学生の男女ともに5号球が使用されています。このサイズは、子どもたちのまだ発達途上にある手の大きさや筋力を考慮して定められた規格です。ボールが軽くて小さいため、力の弱い小学生でもコントロールしやすく、バスケットボールの最も基本的な技術であるドリブル、パス、シュートを楽しく、そして正しく習得することに適しています。
しかし、この5号球という規格は、選手育成における一つの課題も内包していました。中学生になると、男子は一気に7号球、女子は6号球へとボールのサイズが大きくなります。この急激な変化は「カテゴリの壁」とも言え、多くの子どもたちがボールの重さや大きさに戸惑い、シュートフォームを崩してしまう原因の一つとされてきました。
そうした背景はありますが、5号球がバスケットボールの楽しさを知り、競技の入り口として基礎を身につける上で、長年にわたり非常に重要な役割を担ってきたことは間違いありません。
ルール改正で6号球へ変更

今回のルール改正における最大の変更点が、使用球のサイズが長年親しまれてきた5号球から6号球へと変更されることです。6号球は、現在、中学生以上の女子や、世界のトップリーグであるWNBA(女子プロバスケットボールリーグ)などで公式球として使用されている、より本格的なサイズのボールです。
この変更の最大の目的は、前述の「カテゴリの壁」を取り払い、次のカテゴリーであるU15(中学生)への移行をスムーズにすることにあります。子どもたちは小学生のうちから、より重く、大きいボールの扱いに慣れることで、中学に上がってもスムーズに競技を続けることができます。ボールのサイズが変わると、ドリブルの突き出しの強さ、ボールを保持するための指先の力、そしてシュートを遠くまで飛ばすための全身を使ったフォームなど、多くの技術的な要素を一段階高いレベルへと引き上げる必要が出てきます。
| 種類 | 円周 | 重量 | 主な使用者(現行ルール) |
|---|---|---|---|
| 5号球 | 69~71cm | 470~500g | 小学生(ミニバス) |
| 6号球 | 72.4~73.7cm | 510~567g | 中学生以上の女子 |
| 7号球 | 74.9~78cm | 567~650g | 中学生以上の男子 |
表からもわかるように、5号球から6号球への変更は、重さが約40g~70g、円周が約3cm大きくなることを意味します。数値上はわずかな差に見えるかもしれませんが、実際に持ってみるとその違いは歴然で、小学生にとっては大きな挑戦となるでしょう。
ルール改正は2025年から本格化

新しいルールの適用は、国内で最もレベルの高い小学生が集う2025年度開催の「第57回全国ミニバスケットボール大会」から本格的に始まります。日本バスケットボール協会は、具体的なスケジュールを以下のように発表しています。
- 2024年度 全国大会:まず「スリーポイント」のみが特別ルールとして先行導入される。
- 2025年度 全国大会:「スリーポイント」「リングの高さ305cm」「6号ボール」の3つの新ルールがすべて適用される。
全国大会というトップレベルの舞台でまず適用し、そこから全国の各地域へと波及させていく計画です。この全国大会での適用を皮切りに、各都道府県やブロックレベルの大会でも、新ルールへの移行が加速していくことが見込まれます。ただし、何度も繰り返すように、すべての地域大会で一斉に導入されるわけではありません。特に地域の体育館の設備改修には時間と予算を要するため、準備が整った地域から適用が始まります。したがって、自分が目標とする大会のレギュレーションを、主催者の公式サイトなどで事前にしっかり確認することが不可欠です。
コーチ
全国大会のスケジュールが先行して発表されていますが、地域の予選大会でどのルールが適用されるかは、まだ未定の部分も多いです。常に最新の情報をキャッチアップしていく姿勢が大切ですよ。チームとしても、あらゆるルールに対応できるよう、練習計画を柔軟に組んでいく必要がありますね。
ゴールの高さも同時に変更される

ボールサイズの変更と並行して進められる、もう一つの大きな改革がリング(ゴール)の高さです。現行のミニバスルールでは260cmに設定されていますが、これが中学生以上と同じ国際基準の305cmに引き上げられます。45cmも高くなるため、選手たちのプレーに与える影響は計り知れません。
リングが高くなることで、特にシュート技術に大きな変化が求められます。これまでと同じ感覚でシュートを打てば、ボールがリングに届かない、いわゆる「エアボール」になったり、アーチが低すぎてリングに弾かれたりすることが格段に増えるでしょう。より高く、美しいアーチ(軌道)を描くためには、腕の力だけでなく、膝や体幹を使った全身の連動が不可欠になります。ボールが重くなることと相まって、シュート練習の質と量がこれまで以上に重要性を増すことになります。
この変更も、U15カテゴリーへのスムーズな移行を目的としており、小学生のうちからより実戦に近い環境でプレー経験を積ませ、国際的に通用する選手を育成するという長期的な視点に基づいています。
ゴールの高さが変更されるのはなぜ?
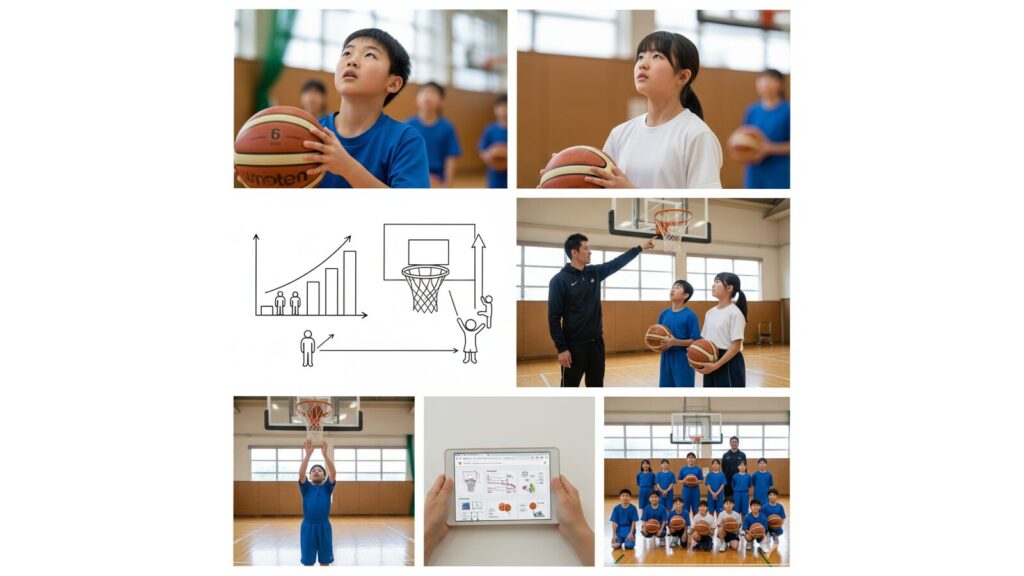
ゴールの高さが45cmも引き上げられる背景には、近年の子どもたちの著しい発育と、バスケットボール全体の技術レベルの向上があります。
日本バスケットボール協会が発表している背景・理由には、主に以下の3点が挙げられています。
- 全国大会に出場する選手の技術レベル(ファンダメンタル)が年々向上していること。
- 文部科学省の学校保健統計調査などに見られる、子どもの平均身長の上昇といった発育状態の変化。
- 競技規則が大きく変わるU15カテゴリーへの「つながり」を持たせること。
要するに、現在の260cmという高さは、特に競技レベルの高い小学校高学年の選手にとっては、すでに「低すぎる」状態になっていたのです。ゴールが低いと、ダンクシュートが容易にできてしまったり、本来ならブロックされるような低いシュートでも決まってしまったりと、ゴール下での技術的な工夫や駆け引きを学ぶ機会が失われがちです。305cmという国際基準の高さでプレーすることにより、選手たちはより高度なフィニッシュスキルや、高さを克服するためのシュート技術を身につける必要性に迫られます。これが結果として、日本バスケットボール界全体のレベルアップに繋がることが期待されているのです。
ミニバスのボールサイズ変更に伴う影響と準備

- バスケットボールのサイズ6号は何歳から?
- 小学生から6号球で練習すべきか
- バスケットボールの公式球は変更される?
- コートサイズなど他のルール変更点
- ルールブックで最新情報を確認
- 総まとめ:ミニバスのボールサイズ変更
バスケットボールのサイズ6号は何歳から?
これまでのルールでは、6号球は主に「中学生以上の女子」が使用するボールでした。しかし、今回のルール改正により、その対象が「小学生高学年」にまで拡大されることになります。
ここで最も重要なのは、「何歳から」という画一的な年齢基準で判断するのではなく、個々の選手の成長段階やバスケットボールの習熟度に合わせてボールを選ぶという視点です。例えば、バスケットボールを始めたばかりの低学年の選手や、同学年の中でも特に小柄な選手が、周りに合わせて無理に6号球を使い始めると、重さに負けて手首だけで投げるような悪いシュートフォームが身についてしまったり、指や手首を痛めるなど怪我に繋がったりする危険性があります。
ルール改正の移行期間中は特に、チームの方針を尊重しつつも、個々の選手の状態を指導者と保護者がよく観察し、コミュニケーションを取りながら、その子にとって最適なボールサイズを選択してあげることが、長期的な成長のために非常に重要となります。
小学生から6号球で練習すべきか

「早く新しいボールに慣れさせたい」と考える保護者の方も多いと思いますが、この疑問に対しては、メリットとデメリットの両方を冷静に理解した上で、慎重に判断する必要があります。
6号球で早期に練習するメリット
- 中学バスケ(U15)への適応力向上:U15カテゴリーで使うボールに早くから慣れることで、中学進学後のギャップを最小限に抑えられます。
- フィジカルの強化:重く大きいボールをコントロールしようとすることで、自然と体幹や指先の力が鍛えられます。
- 正しいフォーム習得の意識付け:手先だけではボールが飛ばないため、全身を使った正しいシュートフォームを意識する良いきっかけになります。
6号球で早期に練習するデメリット・注意点
- 怪我のリスク:身体がまだ十分に発達していない選手にとっては、手首や肘、肩への負担が大きく、怪我に繋がる可能性があります。
- 不適切なフォームの定着:シュートがリングに届かないため、胸から押し出すような無理なフォーム(いわゆる”砲丸投げ”)が癖になってしまう危険性があります。一度ついた癖を後から修正するのは非常に困難です。
- モチベーションの低下:ボールをうまく扱えず、シュートも入らない状況が続くと、バスケットボールそのものの楽しさを感じにくくなり、モチベーションの低下に繋がる場合があります。
これらの点を総合的に考えると、小学校5・6年生や、ある程度の技術と体格がある選手は、練習の一部に6号球を取り入れ、徐々に使用時間を増やしていくのが現実的で効果的なアプローチでしょう。一方で、低学年や初心者のうちは、焦らずに5号球で「ボールと友達になる」ことから始め、基礎技術をしっかりと固めることが何よりも大切です。チームによっては、学年や習熟度に応じて練習ボールを明確に使い分けるといった、きめ細やかな指導計画が求められます。
バスケットボールの公式球は変更される?

はい、大会のルールが変更されるのに伴い、そこで使用される公式球も当然6号球に変更されます。
例えば、ルールが本格的に適用される2025年度の全国ミニバスケットボール大会では、株式会社モルテンが製造する「BG5000」の6号球サイズが唯一の公式試合球として採用されることが発表されています(2025年時点の情報)。このボールは、FIBA(国際バスケットボール連盟)の国際大会でも使用されるモデルで、汗をかいても滑りにくい優れたグリップ性能や、ボールの回転が目で追いやすい12枚パネル構造など、最高のパフォーマンスを発揮できるよう設計されています。(参照:株式会社モルテン公式サイト)
普段の練習から公式球、あるいはそれに近い品質のボールに触れておくことは、試合本番でのパフォーマンスに直結します。ボールの質感や跳ね返り方、重さの感覚に慣れておくことで、試合でのわずかな感覚のズレをなくし、練習の成果を最大限に発揮できるのです。これから新しくボールを購入する際は、JBA検定球のマークがついているかどうかなど、品質が保証された製品を選ぶことを強くお勧めします。
コートサイズなど他のルール変更点
今回のルール改正で、ボールとゴールの高さ以外にもう一つ、戦術面に大きな影響を与える変更が「スリーポイントラインの導入」です。
これまでミニバスの得点はすべて2点でしたが、新ルールでは一般のルールと同じく、リングの中心から6.75mの位置にスリーポイントラインが新設されます。これにより、アウトサイドからのシュートの価値が一気に高まり、チームの戦術や選手の役割に大きな変革をもたらすことが予想されます。
具体的には、これまではゴール下に長身選手を配置するインサイド主体のチームが有利でしたが、今後はスリーポイントシュートを警戒してディフェンスは外に広がらざるを得ません。その結果、ディフェンスの間にスペースが生まれ、ドライブで切り込んだり、インサイドの選手が1対1を仕掛けやすくなったりと、コートを広く使ったより現代的なオフェンスが展開されるようになります。
今後、他のルールも変わる可能性は?
今回の大きな変更をきっかけに、将来的には「3秒ルール(オフェンスが制限区域内に3秒以上とどまれない)」や「24秒ショットクロック(24秒以内にシュートを打たなければならない)」など、他のバイオレーションも段階的に国際ルールに統一されていく可能性があります。常に世界のバスケットボールの潮流を意識し、選手たちがスムーズにステップアップできる環境を整えるためのルール改正が、今後も進められていくでしょう。
ルールブックで最新情報を確認

ルール改正の移行期間中は、情報が更新されたり、解釈が変更されたり、また地域によって細かな運用方法が異なったりする可能性があります。そのため、最も正確で信頼できる最新の情報を得るためには、必ず公式サイトを確認することが不可欠です。
指導者や保護者の皆さんが情報の一次ソースとして定期的にチェックすべきサイトは、以下の通りです。
- 日本バスケットボール協会(JBA)公式サイト:
すべてのルールの基本となる公式な発表や、詳細な競技規則、各種ガイドラインが掲載されます。まずはここを確認するのが基本です。
(参照:公益財団法人日本バスケットボール協会 公式サイト) - 各都道府県バスケットボール協会サイト:
自分が所属する、あるいは参加する地域の大会レギュレーションや、予選大会での特別ルールの適用状況など、より具体的で身近な情報が発表されます。
特に、SNSや個人のブログなどで見られる情報は、古かったり、個人的な解釈が含まれていたりする場合があります。大切な試合で「ルールを知らなかった」という事態を避けるためにも、インターネット上の不確かな情報に惑わされず、必ずこれらの公式な発表を確認する習慣をつけましょう。
総まとめ:ミニバスのボールサイズ変更
最後に、この記事で解説したミニバスのボールサイズ変更に関する重要なポイントを、改めて一覧でまとめます。
- ミニバスの使用球は現行の5号球から6号球へ変更される
- 2024年4月から2027年3月末までの3年間が移行期間として設定されている
- 2025年度の全国大会から6号球と305cmリングの使用が本格的に始まる
- 全国での完全移行は2027年度末が目標とされている
- ボールサイズ変更の主目的は子どもの成長への対応と中学バスケへの円滑な移行
- ボールと同時にリングの高さも260cmから国際基準の305cmへ変更される
- リングの高さ変更も選手の著しい成長と将来的な技術向上に対応するため
- 6号球はこれまで中学生以上の女子が主に使用してきた本格的なサイズ
- 小学生がいきなり6号球で練習することにはメリットとデメリットの両方がある
- 高学年から段階的に練習に取り入れ、徐々に慣れていくのが現実的な方法
- 大会の公式球も当然6号球に変更され、モルテン社製BG5000が採用予定
- 他の大きなルール変更点として、戦術に影響を与えるスリーポイントラインの導入がある
- コートサイズ自体の変更(縦横の長さ)は現時点では発表されていない
- 最新かつ正確な情報はJBAや各都道府県協会の公式サイトで確認することが重要
- 一連のルール改正は、日本のバスケットボール全体の競技レベル向上を目指した長期的な改革
人気ブログランキング(クリック応援よろしくお願いいたします。)

ミニバスケットボールランキング