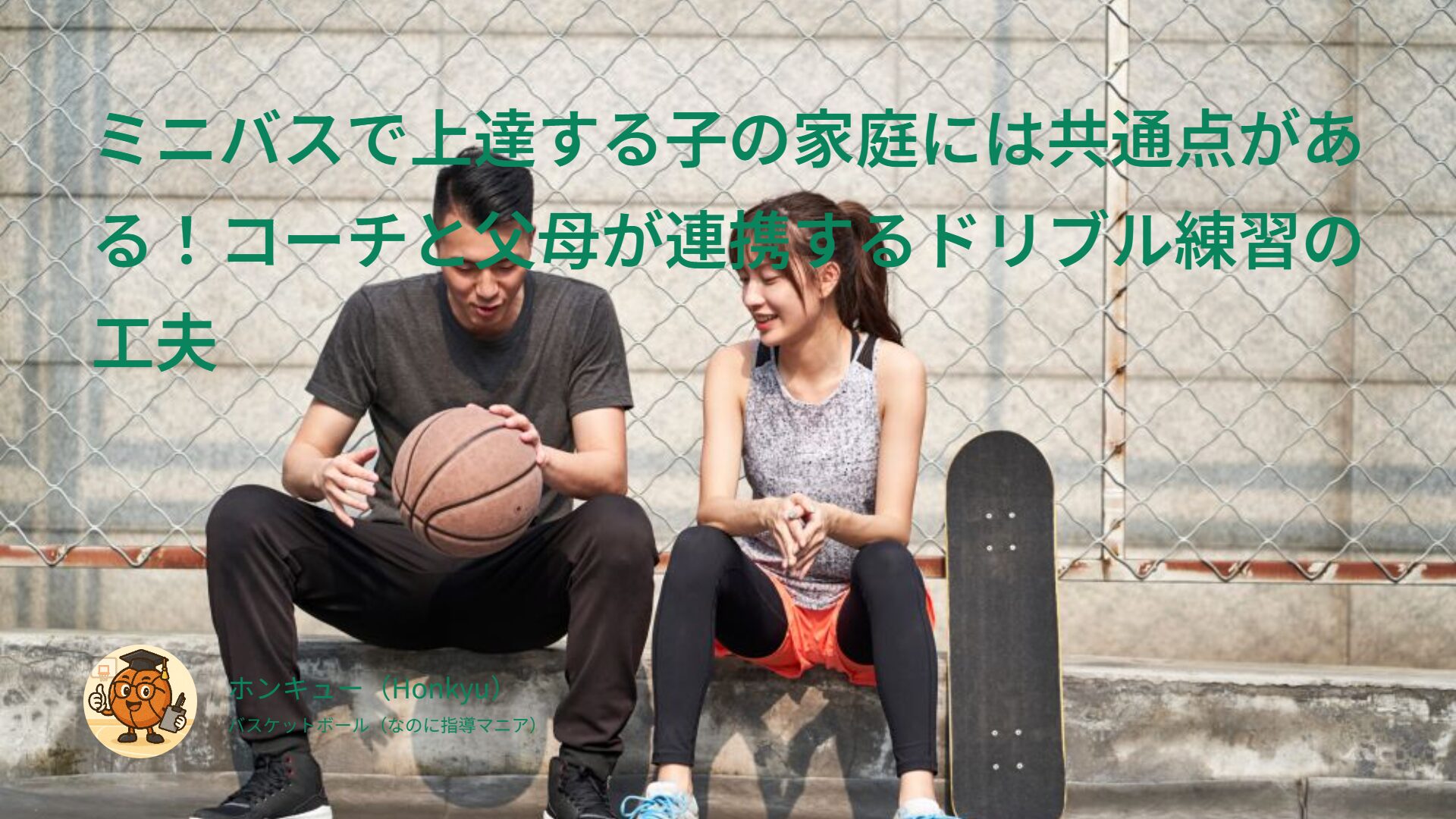ミニバス下手の子の親の悩み|子供の可能性を信じるヒント

「うちの子、もしかしてバスケに向いてない子なのかな…」ミニバスに励むお子さんを応援しながらも、周りの子と比べてしまい、ふとそんな不安がよぎることはありませんか。特に気が弱い子のバスケットボールとの相性を考えたり、なかなか試合に出れない子の親としてバスケの練習を見守っていると、様々な思いが交錯するものです。
サポートする親が抱えるストレスは決して小さくなく、「正直しんどい」と感じてしまう日もあるかもしれません。しかし、子供の成長を願うからこそ、親がやってはいけない3つのNG行動は避けたいところです。この記事では、そもそもバスケに向いている子はどんな子なのか、そしてミニバスが上手い子の特徴とは何かを解き明かします。
センスのある子と伸びる子の違いを理解し、子供が急に上手くなるきっかけや、ミニバスで上手くなる時期はいつ訪れるのか、具体的な情報をもとに詳しく解説します。この記事を最後まで読めば、ミニバス下手の子の親として今何ができるのか、その答えがきっと見つかるはずです。
- 下手な子の親が抱える悩みの正体がわかる
- 子供の成長をサポートする具体的な方法が見つかる
- 親として避けるべきNG行動を具体的に理解できる
- 子供の可能性を信じ、前向きに応援できるようになる
ミニバス下手の子の親が抱える悩みと現実

- 「バスケに向いてない子?」と感じる瞬間
- 気が弱い子のバスケットボールとの相性
- 試合に出れない子の親がバスケで思うこと
- サポートする親が抱えるストレスとは
- 「正直しんどい」と感じてしまう時
- 親がやってはいけない3つのNG行動は?
「バスケに向いてない子?」と感じる瞬間
お子さんがミニバスを頑張る姿を見て、「もしかして、このスポーツは向いていないのかもしれない」と感じてしまう瞬間は、多くの親が経験する根深い悩みです。例えば、練習で他の子たちが次々と新しい技を覚える中で、自分の子供だけがなかなかついていけていないように見える時、焦りや不安を感じるのはごく自然な感情でしょう。
試合でパスミスやドリブルミスが続いたり、ボールに積極的に絡めずにコートの隅にいる姿を目の当たりにすると、親として胸が締め付けられるものです。また、ルールを覚えるのが苦手で、試合中に戸惑っている様子を見ると、「楽しめていないのでは?」と心配になってしまいます。
特に、子供自身が練習に対してあまり楽しそうにしていない、あるいは「今日は休みたい」と口にする頻度が増えてくると、その思いは一層強くなります。親としては、子供の可能性を信じたい気持ちと、嫌なことを無理強いしているのではないかという罪悪感との間で、心が大きく揺れ動くことになります。
「今」という一点だけで判断しないことの重要性
しかし、忘れてはならないのは、子供の成長は一直線の右肩上がりではないということです。今はうまくできなくても、ある日突然コツを掴んだり、体の成長が追いつくことでプレーが劇的に変わることがあります。大切なのは、「今」という短い期間の姿だけで子供の適性や可能性を判断しないことです。多くの失敗を経験することこそが、長期的に見れば成長への一番の近道なのです。
他の子と比べてしまうのは親心として仕方のない部分もあります。ですが、その比較が子供への無言のプレッシャーにならないよう、一歩引いて子供自身のペースを見守る姿勢が求められます。
気が弱い子のバスケットボールとの相性

「うちの子は気が弱いから、激しいコンタクトのあるバスケットボールは向いていないのでは?」と心配される親御さんは少なくありません。確かに、バスケットボールは選手同士の体のぶつかり合いが多く、ボールを奪い合う強い気持ちや積極性が求められるスポーツです。
そのため、引っ込み思案な性格であったり、他人を押しのけてまで前に出ることを好まない優しい性格の子は、最初のうち戸惑う場面が多いかもしれません。具体的には、以下のようなプレーにその特性が現れがちです。
- 床に転がったボール(ルーズボール)に躊躇なく飛び込めない
- 相手に強くディフェンスをされると、すぐに味方にパスをしてしまう
- フリーでシュートを打てる絶好の場面でも、他の子に譲ってしまう
- チームメイトに指示を出したり、大きな声を出してボールを呼んだりすることができない
しかし、気が弱いという性格は、必ずしもバスケットボールにおいて短所になるわけではありません。視点を変えれば、それはチームにとって不可欠な素晴らしい長所にもなり得るのです。
「気の弱さ」をチームを支える「長所」に変える視点
例えば、気が弱く慎重な子は、コート全体の状況を冷静に観察する能力に長けている場合があります。誰がどこにいて、次にどこへ動くのかを的確に把握し、味方が最も有利になるような絶妙なアシストパスを出せるかもしれません。また、自己主張が強くない分、チームの和を重んじ、コーチの指示を忠実に実行できる素直さも持っています。このような特性は、チームプレーを円滑に進める上で非常に重要な要素となります。
最初はプレーの激しさに気後れするかもしれませんが、練習を重ねるうちに少しずつ自信がつき、スポーツを通じて内面的な強さが育まれる子もたくさんいます。お子さんの性格を否定せず、「あなたらしさを活かせる場所がきっとあるよ」と伝え、その子に合った形でバスケの楽しさを見つけられるようサポートすることが大切です。
試合に出れない子の親がバスケで思うこと

毎週のように送迎し、汚れたユニフォームを洗濯し、頑張りを応援しているのに、我が子がなかなか試合に出られない。ベンチで仲間を応援する子供の小さな背中を見るたびに、親としては言葉にできない複雑な気持ちになるものです。
「これだけ真面目に練習しているのに、どうして使ってもらえないのだろう」という指導者への不満や、「このまま続けていても、この子のためになるのだろうか」という活動そのものへの疑問が頭をよぎることもあるでしょう。親がこれほど悔しいのだから、本人はもっと辛いのではないかと、子供の気持ちを想像しては胸が痛みます。
特に、後から入団した下級生や、同じ学年の子が活躍する姿を目の当たりにすると、子供本人の悔しさはもちろん、親としてもやるせない気持ちに駆られます。「いっそ、活躍できる別のスポーツに変えた方が良いのでは?」と、子供の将来を思って提案したくなることもあるかもしれません。
しかし、もしお子さん自身が「まだ頑張りたい」「あの子に勝ちたいから練習する」という強い意志を示しているのであれば、親はその熱い気持ちを最大限尊重し、どっしりと構えて見守る覚悟が必要です。試合に出ることだけが、ミニバスで得られるものの全てではありません。たとえ補欠であっても、チームの一員として貢献できる役割はたくさんあります。
その中で、困難に立ち向かう精神力(レジリエンス)や、悔しい気持ちを乗り越えて仲間を応援する大切さといった、技術以上に価値のある人間性を学んでいるのかもしれません。
もちろん、何もせずにただ待つだけでなく、親として指導者と良好なコミュニケーションを取り、子供の現状や課題、今後の成長について情報を共有することも大切です。ただし、試合の采配は監督やコーチの専門領域。そこは尊重しつつ、家庭では子供の一番の理解者であり、どんな結果であっても受け入れる「心の拠り所」であり続けることが、最も重要な役割と言えるでしょう。
サポートする親が抱えるストレスとは
ミニバスの活動は、子供の努力だけでなく、それを支える親の献身的なサポートがあってこそ成り立っています。しかし、そのサポートが時として大きなストレスの原因となり、親を疲弊させてしまうことも少なくありません。親が抱えるストレスは、大きく分けて「時間的・物理的な負担」と「精神的な負担」の二つに分けられます。
時間的・物理的な負担
平日の夜間や週末の練習、試合の際の送迎は、親にとって最も分かりやすい負担の一つです。特に共働きや他に兄弟がいる家庭、あるいは親の介護など、それぞれの家庭の事情を抱えている場合、時間のやりくりは非常にシビアになります。また、お茶当番や試合会場の設営、チームのイベント準備など、直接的な練習以外での役割分担も発生し、休日がほとんどミニバスの活動で埋まってしまうことも珍しくありません。
精神的な負担
精神的な負担はさらに根深く、複雑です。我が子の上達が思うように進まないことへの焦りやプレッシャーはもちろんのこと、他の保護者との人間関係に悩むケースも多く見られます。チーム内での意見の対立や、一部の保護者からの過度な要求など、大人同士の付き合いがストレスになることは多々あります。
中には「うちの子がいないと勝てないでしょ?」といった発言で、他の親子に対して優位に立とうとする、いわゆる「マウントを取る」保護者もいるかもしれません。
マウントを取る親の心理と対処法
子供の活躍を自分の価値と重ねてしまう「自己同一化」という心理が背景にある場合があります。子供が評価されることで、親自身の自己肯定感を満たそうとしているのかもしれません。このような発言に遭遇した際は、真正面から受け止めて傷つくのではなく、「この人は不安なんだな」「自分に自信がないのかもしれない」と冷静に受け流し、意識的に心の距離を取ることが、自分自身を守るための有効な対処法になります。
これらの様々なストレスが積み重なると、純粋に子供を応援したいという気持ちが薄れ、サポートが「やらなければいけない義務」のように感じてしまうことにもなりかねません。すべてを完璧にこなそうとせず、時には断る勇気を持ち、無理のない範囲で関わることが、親子共にミニバスを長く楽しむための重要な秘訣です。
「正直しんどい」と感じてしまう時

子供の成長を心から願い、応援したいと思って始めたミニバスのサポート。しかし、活動を続ける中で、時には「正直、もうしんどい…」と心が折れそうになる瞬間が訪れることがあります。それは決して、子供への愛情が足りないわけでも、サポートへの情熱が冷めたわけでもありません。様々な要因が複雑に絡み合い、心身ともに疲弊してしまうのは、多くの親が経験することです。
例えば、以下のような状況が重なった時に「しんどさ」の限界を感じやすくなります。
- 仕事や家事、介護との両立が限界に近い時:自分の時間が全くなく、常に何かに追われている感覚に陥り、心身の休まる暇がありません。
- 子供のやる気が感じられない時:親が時間をやりくりして一生懸命サポートしているのに、当の子供が練習に身が入っていなかったり、反抗的な態度を取ったりすると、自分の努力が報われないような徒労感を覚えてしまいます。
- 保護者間のトラブルに巻き込まれた時:チームの方針や役割分担をめぐる意見の対立、噂話など、大人同士の人間関係は大きな精神的負担となります。
- 経済的な負担が重い時:月謝や遠征費、ユニフォームやバッシュなどの用具代、さらには合宿費など、予想以上に出費がかさみ、家計を圧迫することもあります。
「頑張りすぎない」という大切な選択肢
もし「しんどい」と強く感じたら、それは「少しペースを落としてください」「休息が必要です」という心と体からの重要なサインです。すべてを一人で抱え込まず、まずはパートナーや信頼できる他の保護者、あるいは指導者に「今、こういう状況で少し大変なんです」と相談してみましょう。時には「できないことはできない」と正直に伝え、協力を求める勇気も必要です。
完璧なサポートを目指して親が疲弊してしまうよりも、親自身が心に余裕を持って笑顔でいることの方が、子供の心の安定にとってはるかに大切なのです。
応援する側にも休息とリフレッシュは不可欠です。無理のない範囲で関わり、親子でミニバスを「楽しめる」と感じられる最適なバランスを見つけることが、活動を長く健やかに続けていくための鍵となります。
親がやってはいけない3つのNG行動は?

子供の上達を願うあまり、良かれと思って取った親の行動が、かえって子供の自主性や可能性の芽を摘んでしまうことがあります。ここでは、特に注意したい「親がやってはいけない3つのNG行動」について、その心理的な影響も含めて詳しく解説します。
NG行動1:他人との比較や否定的な言葉
「〇〇ちゃんはあんなに上手なのに、どうしてあなたはできないの?」「本当にどんくさいね」といった言葉は、子供の心に深い傷を残します。親は「奮起してほしい」という激励のつもりでも、子供は自分の能力や存在そのものを否定されたように感じてしまいます。これは自己肯定感を著しく低下させ、挑戦する意欲を奪い、バスケットボールへの興味を失わせる最も大きな原因の一つです。
NG行動2:過度なプレッシャーと練習の強制
「毎日自主練しなさい」「次の試合で活躍できなかったら許さないからね」など、結果を求めるあまり過度なプレッシャーをかけるのは逆効果です。子供が自ら「上手くなりたい」「練習したい」と思う内発的な動機がなければ、練習はただの苦痛でしかありません。
「やらされる練習」は集中力も続かず、技術もなかなか身につきません。それどころか、親の期待に応えられない自分を責め、バスケットボールが嫌いになるという最悪の結果を招いてしまいます。
NG行動3:練習や試合後の執拗な「ダメ出し」
練習や試合が終わった後、特に逃げ場のない帰りの車の中などで「あの時のプレーは完全にダメだった」「どうしてあそこでパスを選択しないんだ」といったダメ出しを執拗に行うのは避けましょう。子供は試合での失敗を、親が思う以上に自分で一番よく分かっています。そして、コーチからも既に具体的な指導を受けているはずです。
親からの追い打ちのような指摘は、子供の心の逃げ場を完全になくしてしまいます。「家に帰っても怒られる」と感じると、子供はプレーの失敗を過度に恐れるようになり、思い切ったプレーができなくなってしまいます。
家庭は心と体を休める「安全基地」であるべき
練習や試合でどんなに悔しい思いをしても、家に帰れば受け入れてもらえる。家庭がそのような「心の安全基地」であることが、子供が安心して失敗し、挑戦を続けるための絶対的な土台となります。試合後は技術的な反省を促す前に、まず「お疲れ様」「最後までよく頑張ったね」と、その日の努力そのものをねぎらう温かい言葉をかけてあげてください。
ミニバス下手の子の親に伝えたい子供の可能性

- そもそもバスケに向いている子はどんな子?
- ミニバスが上手い子の特徴とは何か
- センスのある子と伸びる子の違い
- 子供が急に上手くなるきっかけ
- ミニバスで上手くなる時期はいつ来るのか
- まとめ:ミニバス下手の子の親ができること
そもそもバスケに向いている子はどんな子?
バスケットボールに向いている子と聞くと、多くの人は「背が高い子」や「足が速い子」「運動神経が良い子」といった、いわゆる身体的な特徴や才能を思い浮かべるかもしれません。もちろん、それらの要素がプレーにおいて有利に働くことは紛れもない事実です。しかし、それが全てではありません。
ミニバスの年代においては、身体的な特徴以上に、物事に対する考え方や性格といった内面的な要素が、将来的な成長に大きく関わってきます。一般的に、バスケットボールを通じて大きく成長するとされる子の特徴には、以下のような点が挙げられます。
| 特性 | 具体的な内容と成長への繋がり |
|---|---|
| 負けず嫌いな性格 | 試合に負けたり、1対1で相手に抜かれたりした時に「悔しい」と心から感じ、次こそはと努力できる子は飛躍的に上達します。この悔しさが練習へのエネルギーになります。 |
| 自分で考える力がある | なぜ今のシュートが外れたのか、どうすれば相手を効果的に止められるのかなど、プレーの一つひとつを自分で考え、改善しようとする姿勢が大切です。いわゆる「バスケIQ」が高い選手へと成長します。 |
| 協調性と思いやりがある | バスケットボールは5人で行うチームスポーツです。自己中心的なプレーに走るのではなく、仲間を活かし、チーム全体のために献身的に動ける子が最終的にチームに不可欠な存在となります。 |
| 話を聞く素直さ | コーチや親、仲間からのアドバイスを「まずはやってみよう」と素直に聞き入れ、試してみる柔軟な心は、成長の大きな原動力になります。自分の殻に閉じこもらず、常に学び続けられます。 |
いかがでしょうか。これらの特徴は、生まれ持った才能というよりも、日常生活やスポーツの経験を通じて後から育むことができるものばかりです。現時点でこれらの特徴に当てはまらないからといって、「うちの子は向いていない」と判断するのはあまりにも早計です。ミニバスでの様々な成功体験や失敗体験を通じて、これらの力は少しずつ、しかし確実に養われていきます。
親として大切なのは、今の姿だけで子供の限界を決めるのではなく、これからの成長の可能性を心から信じてあげることです。
ミニバスが上手い子の特徴とは何か

ミニバスの練習や試合を見ていて、「あの子は上手いな」と評価される子には、いくつかの共通した特徴が見られます。それは単にドリブルが速い、シュートがたくさん入るといった技術的な側面だけではありません。むしろ、バスケットボールという競技に対する姿勢や、プレー中の思考の質に、その秘訣が隠されていることが多いのです。
上手い子に共通する主な特徴は、以下の3つに集約されます。
1. バスケを心から楽しんでいる
何よりもまず、バスケットボールが大好きで、プレーすることを心から楽しんでいます。この純粋な「好き」という気持ちが、辛く困難な練習を乗り越え、自主的に努力を続けるための最大のモチベーションになります。親から「練習しなさい」と言われなくても、気づけばボールに触っている時間が自然と長くなるのです。
2. 自分で考えてプレーしている(バスケIQが高い)
コーチに言われたことをロボットのようにただこなすだけでなく、コートの中で常に「今、何をすべきか」を自分で考えて判断しています。味方や相手の位置、試合の時間や点差といった状況を瞬時に読み取り、チームにとって最も効果的で確率の高いプレーを選択する力を持っています。この思考力、いわゆる「バスケットボールIQ」は、多くの試合経験と、自らの失敗から学ぶ姿勢の中から磨かれていきます。
3. 人の話を素直に聞ける(謙虚さ)
上手い子ほど、自分の実力に自信を持ちつつも、コーチや経験豊富な大人からのアドバイスを素直に聞き入れ、実践しようとします。自分のプレーにプライドはあっても、改善すべき点については謙虚に受け止める姿勢が、さらなる高みへと成長するために不可欠であることを知っています。自分の考えに固執せず、良いと思ったことはどんどん取り入れる柔軟性があります。
技術は「心・技・体」の土台があってこそ
これらの特徴に共通するのは、スポーツ選手としての内面的な成熟度です。もちろん、日々の技術的な練習は上達に不可欠ですが、それはあくまで「楽しむ心」「考える頭」「素直な姿勢」という土台があってこそ、その効果が最大限に発揮されます。もしお子さんの技術面で伸び悩んでいるのであれば、まずはバスケを楽しむこと、そして自分で考えることの重要性を伝えてみるのが良いかもしれません。
センスのある子と伸びる子の違い

ミニバスの世界では、「あの子はセンスがある」という言葉をよく耳にします。一方で、最初は全く目立たなかったのに、学年が上がるにつれてぐんぐん上達してくる「伸びる子」もいます。この二つのタイプにはどのような違いがあるのでしょうか。そして、親としてはどちらの可能性を信じ、サポートしていくべきなのでしょうか。
センスのある子とは?
「センスのある子」は、いわゆる運動神経が良く、物事のコツを掴むのが早いタイプです。少し教えただけですぐに難しいドリブルやシュートをマスターしたり、試合の中でも大人が驚くような直感的なプレーを見せたりします。飲み込みが非常に早いため、特に低学年のうちはチームの中でも際立って目立つ存在になりやすいです。しかし、その才能に甘えて地道な努力を怠ると、ある時点で成長が頭打ちになってしまう危険性も秘めています。
伸びる子とは?
一方、「伸びる子」は、最初は不器用で、他の子に比べて上達のスピードが遅いかもしれません。しかし、バスケットボールが大好きで、誰よりも真面目にコツコツと努力を続けることができるタイプです。失敗を恐れずに何度も挑戦し、コーチのアドバイスを素直に聞いて、誰も見ていないところでも地道な基礎練習を繰り返します。このような子は、高学年になるにつれて身体の成長とともに技術が追いつき、いつしか「センスのある子」を追い越していくことも少なくありません。
成長の鍵は「非認知能力」にあり
「伸びる子」に共通するのは、目標に向かって努力し続ける力(グリット)、困難に立ち向かう力、感情をコントロールする力といった、テストの点数では測れない「非認知能力」の高さです。文部科学省も、この非認知能力が子供たちの将来の成功に重要であると指摘しています。(参照:文部科学省「幼児期における非認知能力の育ちと、その後の育ちに関する調査研究」)ミニバスは、この非認知能力を育む絶好の機会なのです。
親としては、目先の華やかな「センス」に一喜一憂するのではなく、お子さんが努力を続けるそのプロセスそのものを認め、褒めてあげることが何よりも大切です。地道な努力を続けられること自体が、他の何にも代えがたい素晴らしい才能なのです。
子供が急に上手くなるきっかけ

昨日までできなかったプレーが、ある日突然できるようになった。そんな風に、なかなか上達しなかった子が、ある出来事を境に急激な成長を見せることがあります。この「急に上手くなる」ブレークスルーの現象には、いくつかの典型的なきっかけが考えられます。親としては、そのきっかけが訪れるのを焦らずに待ち、その瞬間を見逃さずにしっかりとサポートしてあげることが重要です。
主なきっかけとして、以下の3点が挙げられます。
1. 身体的な成長(ゴールデンエイジの到来)
特に小学校高学年から中学生にかけての「ゴールデンエイジ」と呼ばれる時期は、運動神経系がほぼ大人と同じレベルまで発達し、新しい動きや技術をすぐに習得できる、まさに「黄金期」です。これまで頭では理解していても体がついてこなかった複雑な動きが、身体の急激な成長によってスムーズにできるようになることがあります。この時期に質の高い練習を積むことで、飛躍的に技術が向上する可能性を秘めています。(参考:公益財団法人日本スポーツ協会「JSPO」)
2. 精神的な成長と成功体験
内面的な成長も、プレーを大きく変えるきっかけとなります。例えば、公式戦で負けた時のどうしようもなく「悔しい」という感情が、翌日からの練習への取り組み方を劇的に変えることがあります。また、どんなに小さなことでも「できた!」という成功体験を積み重ねることで自信がつき、プレーが積極的になることもあります。「絶対にレギュラーになりたい」「あのライバルに勝ちたい」といった明確な目標ができることも、子供の意識を変える大きな要因となります。
3. 周囲からの影響による意識の変化
信頼できるコーチや憧れのプロ選手との出会い、あるいは親からの何気ない一言が、子供の意識を大きく変えることがあります。「なぜ、この地味な基礎練習をするのか」という意味を自分で理解し、納得できるようになった時、練習の質は格段に上がります。また、身近なライバルの存在も「あいつにだけは負けたくない」という健全な競争心を引き出し、互いの成長を加速させる良い刺激となります。
これらのきっかけは、いつ、どのような形で訪れるか誰にも予測できません。だからこそ、親は日々の練習の中での小さな変化や子供の言葉に耳を傾け、子供が前向きな気持ちになった時に「その調子だよ!」「見てるよ!」と温かく背中を押してあげることが大切なのです。
ミニバスで上手くなる時期はいつ来るのか
「一体、うちの子はいつになったら試合で活躍できるくらい上手くなるのだろう…」と、他の子と比べてしまい、その成長の遅さにやきもきする親御さんは多いことでしょう。しかし、結論から言えば、「上手くなる時期は子供によって全く違う」というのが、多くの指導者が口を揃える答えです。
前述の通り、一般的には神経系の発達が著しい「ゴールデンエイジ」(おおよそ9歳~12歳頃)に技術が飛躍的に伸びやすいと言われています。この時期は、一度見たプレーをすぐに真似できたり、覚えた技術が体に染みつきやすいため、バスケットボールのスキルを習得する上で非常に重要な期間です。しかし、これはあくまで一般的な傾向に過ぎません。
成長のタイミングは千差万別、晩成型も
成長が比較的ゆっくりな「晩成型(レイトマチュリティ)」の子もいれば、中学生や高校生になってから急激に身長が伸び、才能を開花させる子も数多くいます。身体の成長が遅い子は、小学生の間は体格差で当たり負けしたり、スピードで劣ったりして苦労するかもしれません。
しかし、見方を変えれば、その期間は勝敗に直結しにくい分、基礎的なボールハンドリングやパス、シュートフォーム、そして状況判断能力といった、ごまかしの効かないファンダメンタルをじっくりと磨く貴重な時間に充てることができます。そして、後から身体が追いついてきた時に、その盤石な技術がとてつもない武器となるのです。
親として最も大切なのは、周りの子の成長スピードと比較して焦らないことです。親が「早く上手くなりなさい」という無言のプレッシャーをかけると、子供はバスケットボールを楽しむ心を失い、本来持っているはずの可能性さえ閉ざしてしまいます。今は結果が出なくても、子供がバスケを好きで、練習を続けているのであれば、その努力と時間は決して無駄にはなりません。お子さん自身の成長のペースを信じ、長い目でどっしりと見守ってあげることが、親にできる最大のサポートと言えるでしょう。
まとめ:ミニバス下手の子の親ができること
この記事では、ミニバスが下手だと感じるお子さんを持つ親が抱える具体的な悩みから、子供の無限の可能性を信じるためのヒントまでを、様々な角度から詳しく解説してきました。最後に、今日から親として実践できること、心に留めておきたいことをリスト形式でまとめます。
- 子供の「今」という一瞬の姿だけで、バスケへの適性や将来性を判断しない
- 他人と比較せず、我が子のユニークな成長ペースを尊重し、応援する
- 気が弱い、優しいといった性格も、チームプレーにおける重要な長所として捉え直してみる
- たとえ試合に出られなくても、日々の練習に参加し努力する過程そのものを認め、具体的に褒める
- 親自身のストレスを溜め込まず、時には周りに助けを求め、無理のない範囲でサポートする
- 「正直しんどい」と感じたら、それは休息のサイン。自分を責めずに、休む勇気を持つ
- 子供の自己肯定感を傷つける否定的な言葉や、過度なプレッシャーは絶対に避ける
- 練習や試合後のダメ出しではなく、まずは「お疲れ様」と努力をねぎらう言葉をかける
- バスケに向いている子の特徴(考える力や素直さ)は、経験を通じて後からでも育めることを知る
- 試合の結果だけでなく、バスケを心から楽しんでいるか、という姿勢を何よりも評価する
- 目先のセンスよりも、困難なことにもめげずに努力を続けられる才能を信じる
- 子供が急成長する身体的・精神的なきっかけが訪れるのを、焦らず、しかし期待して待つ
- ゴールデンエイジという言葉に固執せず、子供の成長のタイミングは千差万別であると理解する
- 家庭を、子供が安心して失敗でき、心と体を休められる「絶対的な安全基地」にする
- 技術指導者になるのではなく、何があっても我が子の味方であり続ける「一番のファン」でいる
人気ブログランキング(クリック応援よろしくお願いいたします。)

ミニバスケットボールランキング